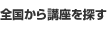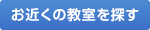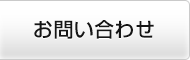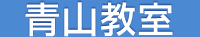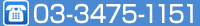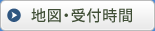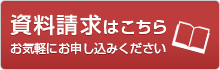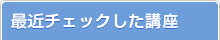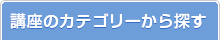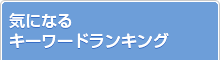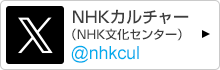�R�̌��z�@���{�l�͉���q�݁A��������Ă����̂�
�R�̌��z�@���{�l�͉���q�݁A��������Ă����̂�
- �u�t
- ���l������w�A������w��w�@���u�t �����Ɩ�
�R�ɋF��A�R�ɒz��
���˂A��͎R�ɂ̂ڂ�A���߂��Ďq���������Ƃ����l����������܂��B�܂��R�ɐ[����������A�������������������C�s�ɂ���Đ_���̗͂�g�ɂ����s�҂����̋L�^�́A��������Ȃ��قǎc���Ă��܂��B����܂Ŗ��X�Ƒ������́u�R�̐M�v�́A�������̍���h���Ԃ�l�X�Ȍ��z��n��o���Ă��܂����B���̍u���ł́A�ْ��w�R�ɗ��_�ƕ��@�����Ăƌ����̐S���j�x���e�L�X�g�ɁA�ꕶ���ォ��]�ˎ���܂ŁA���̎������킩��₷�����b���܂��B
�����̍u���͋����u�����I�����C���z�M���Ă��܂�
�y�����ł̍u���͂�����z��
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1248958.html

�O���R�O�Ŏ�������
�u���̏ڍ�
| ������ | �R���� | �c�@�� | |
|---|---|---|---|
| �J���� | 4/23�`9/10 | �j���E���� | ��4���j 15:30�`17:00 |
| ��@�� | 6�� | �r����u | �ł��܂� |
| ��u�`�� | �I�����C�� | ||
| �R�[�X | ��u���i�ō��݁j | ���ޔ�i�ō��݁j |
|---|---|---|
| ������(����s�v) | 21,780�~ |
����
| �~ | 2025/04/23(��) | ���_�@���{�ƎR(�R�ւ̐M�A�R�����̖{���̎p�F�����A��������) |
|---|---|---|
| �~ | 2025/05/28(��) | ��1��(1 )�_�̍����Ƃ���ƍ��J�̏ꏊ(�ꕶ����̍��J�Ɨy�q�E���q) |
| �~ | 2025/06/25(��) | (2)���𗧂Ă邱�Ƃ̈Ӗ�(�퐶�E�Õ�����̃N�j�̒��A�V���Ɛ_�Ђ̐S�䒌) |
| �~ | 2025/07/16(��) | ��2��(1)�R���Ă���C�s�m(�E�ޗǎ���̎R�ł̏C�s�j |
| �~ | 2025/08/20(��) | (2)�R�ɑ���ꂽ�Ǝ��̌��z�u����(�����Â���)�v�̎n�܂� |
| �� | 2025/09/10(��) | ��3�́u�����v�Ƃ������̗̂R��(������Ƃ͉����A�n�`�ƕ��i�̐���) |
������
�E�e�L�X�g�w�R�ɗ��_�ƕ��@�����Ăƌ����̐S���j�x�����Ɩ����@�u�k�БI�����`�G�@���e���ł��������Ă����������o�b�A�^�u���b�g�i�ʐM���̗ǂ��Ƃ��납��Q�����ĉ������j
���r�f�I��c�c�[��Zoom�A�v���i�C���X�g�[�����@�́u�I�����C���u����u�O�̏����v���������������jhttps://www.nhk-cul.co.jp/misc/onlinecourse_guide/
��NHK�����Z���^�[�R�����Ŏ��{����u�����z�M���܂��B
���l
�@�u���O���ɂ��o�^���[���A�h���X��Zoom�́u���҃��[���v�������肵�܂��B�A�u�����Ԃ�10���O���Zoom�ɓ��������܂��B�B�{�u���\���҂Ɍ���A�u���I����3���ォ��2�T�Ԃ̌������z�M���������܂��B
- �قƂ�ǂ̍u���͌��w�ł��A�u���ɂ���Ă͑̌���u���ł��܂��B�ڍׂ͋����܂ł��⍇�����������B
���I�����C���u���̌��w�A�̌��͂ł��܂���B - [����s�v]�}�[�N�������R�[�X�́A����Ȃ��Ă���u�ł��܂��B
- ������ɂ��ẮA�e�����z�[���y�[�W�́u��u�ɍۂ��āv���������������B
- �c�ȏ͕ϓ����܂��̂ŁA�\�����ɂ͈قȂ�ꍇ������܂��B
- ���̍u�������߂Ď�u�����ꍇ�́A�I�����Ă�����̎�u���͂��������܂���B
���̍u���Ɋ֘A�̂���J�e�S���[
- �c�ȏ͕ϓ����܂��̂ŁA�\�����ݎ��ɂ͈قȂ�ꍇ������܂��B
- �قƂ�ǂ̍u���͓���K�v�ł��B
 �V�����n�܂�u��
�V�����n�܂�u�� 18���ȍ~�Ɏn�܂�u��
18���ȍ~�Ɏn�܂�u�� �d�b�������ɂĂ��₢���킹���������B
�d�b�������ɂĂ��₢���킹���������B